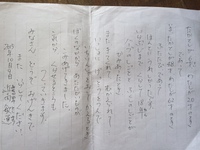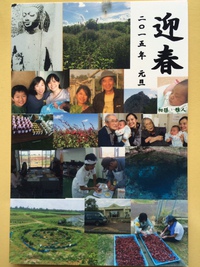29・静謐な池



第29回いらぶ探検隊
・4月26日。
参加16名。
下地島空港滑走路東海岸美化。
一年ぶり、2回目。
発泡スチロール・ペットボトル・浮き球・燃やせるゴミ・缶・瓶しっかり分別全60大袋分。
2時間弱。
大勢でやるとみるみるすすむ。4歳から80歳。
一人ひとりの総合力。
 クリーンな浜に戻った。
クリーンな浜に戻った。今回から市支給のボランティア袋使用。
一般ゴミ袋有料化分をゴミ運搬等環境保全費にあてるとの事。
 ほぼ終了の頃、滑走路西側原野の第3の未知の池先発探索隊3名から、携帯。
ほぼ終了の頃、滑走路西側原野の第3の未知の池先発探索隊3名から、携帯。発見との事。
ダブルやったー!!
グーグル航空写真である。
 海岸寄りの二つの池は昨年12月の探検隊で探索・初探訪。
海岸寄りの二つの池は昨年12月の探検隊で探索・初探訪。今回は、地図右上の長いハート型の青っぽい池。
ハート池。心池。??池。
駆けつけると、地図と磁石と地形をもとに見事な小道が開かれていた。
すごいぞ、雷太・殿・千ちゃん!
やがて現れた池。
 木の上にのぼり、あっ見えた。
木の上にのぼり、あっ見えた。わーきれい。
木
 をトンネル状に切り、
をトンネル状に切り、池畔に!
しばし、池を眺め、憩う。
所々、青が深い。
静謐だー。(写真右上)
海岸で円座して、昼ご飯。
おにぎりと、
持ち寄りの鰹汁・肉味噌・唐揚・ハーブペースト・ソルト・コンフィチュールで憩う。
食後、第2の池再探訪。地図下。

原野の道。
出た。
天地対称の「緑池」だ。
ガーナ(アヒル)池とも言われる。
昨12月、池畔に出れる一ヶ所に雷太が池に入りながらたどり着き、
道を逆に拓いたのだ。
やや広い、
やはり静謐。
しばし、瞑想する人あり。
島の宝。
地球の宝だ。
Posted by ちかさん at
◆2008年04月27日13:52
│いらぶ探検隊
この記事へのコメント
毎回、探検隊の報告拝見しています。
清掃作業ご苦労様です。
それにしても60大袋分とはすごいゴミの量ですね。
あの場所は風向きの関係?か、良くゴミがたまります。
台風の後など大量のゴミが打ち上げられる場所ですね。
その後の滑走路西側の池の探訪もおもしろそうですね。
なかなか人の行かない場所でしょうし、島に暮らしていてもその存在自体が気が付かない池だと思います。
こうして島を知り、そのありように目を向けることは大変大事なことだと思います。
特に伊良部島はその地盤構造が通常の島と異なり、地下に海水が浸透していて、その上に淡水(雨水)がたまった構造になっていると聞いたことがあります。
この下地島はそれが伊良部島と同じ構造かどうか知りませんが、ちょうど通り池の上に蓋をして、その蓋の上で暮らしているような状況?だと思います。
そして、ちょうどその蓋をしそこなった部分がこうして通り池や、この未知の池の状態で残ったのではないか・・・と思っています。
もしかしたら、その池もどこかで海につながっている?のかもしれません。昔、牛などがそんな池にはまるとその死体が長山港付近に現れたという話しがあるそうです。おじいやおばあに聞けばもっと詳しいことが分かるでしょう。
また、話しは変わりますが経営コンサルタントとして有名な船井幸雄氏の本に伊良部島のことを「癒しの島」として紹介されていますが、たぶんそれは島のそんな地下構造と関係があるのではないか・・・と感じています。
また、今後も興味深い島の探訪の話しが続くことを願います。
探検隊活動のさらなる発展を願っています。
清掃作業ご苦労様です。
それにしても60大袋分とはすごいゴミの量ですね。
あの場所は風向きの関係?か、良くゴミがたまります。
台風の後など大量のゴミが打ち上げられる場所ですね。
その後の滑走路西側の池の探訪もおもしろそうですね。
なかなか人の行かない場所でしょうし、島に暮らしていてもその存在自体が気が付かない池だと思います。
こうして島を知り、そのありように目を向けることは大変大事なことだと思います。
特に伊良部島はその地盤構造が通常の島と異なり、地下に海水が浸透していて、その上に淡水(雨水)がたまった構造になっていると聞いたことがあります。
この下地島はそれが伊良部島と同じ構造かどうか知りませんが、ちょうど通り池の上に蓋をして、その蓋の上で暮らしているような状況?だと思います。
そして、ちょうどその蓋をしそこなった部分がこうして通り池や、この未知の池の状態で残ったのではないか・・・と思っています。
もしかしたら、その池もどこかで海につながっている?のかもしれません。昔、牛などがそんな池にはまるとその死体が長山港付近に現れたという話しがあるそうです。おじいやおばあに聞けばもっと詳しいことが分かるでしょう。
また、話しは変わりますが経営コンサルタントとして有名な船井幸雄氏の本に伊良部島のことを「癒しの島」として紹介されていますが、たぶんそれは島のそんな地下構造と関係があるのではないか・・・と感じています。
また、今後も興味深い島の探訪の話しが続くことを願います。
探検隊活動のさらなる発展を願っています。
Posted by 成田の住人 at 2008年04月28日 23:27
☆ 成田の住人さん
島の下部が海水とすると,
今に島が漂流をはじめて・・・、そういえば、下地島とあわせて、
島はひょうたんの形をしていて、
「ひょうたん島!?」と家内と笑いました。
実際は,島尻マージの固い岩盤があって、その上に、水がたまっているという事でしょうか。
それにしても、下地島には、池が多く、
探検隊をはじめて、6っの未知の池に行きました。
陥没ドリーネの神秘!
内陸の池も海水ほどではないですが、塩辛いです。
それにしても、白鳥の潮吹き岩、生きてる間に復活の吹き上げを見たいです。
これは、ドリーネの竪穴と波による横穴がつながったものですね。
それをコンクリートで固めてしまうなんて。
池といえば、この日の最後、通り池に浮かぶゴミを視察したのですが、
20個程の発泡スチロールが浮かんでいます。
醜いです。
岩の上から、池面まで、最短で5メートル。
飛び込んで、ゴミを集めて、上からひっぱって、縄梯子で登ってくる案が出ました。
いかに、です。
妙案はありましょうか。
島の下部が海水とすると,
今に島が漂流をはじめて・・・、そういえば、下地島とあわせて、
島はひょうたんの形をしていて、
「ひょうたん島!?」と家内と笑いました。
実際は,島尻マージの固い岩盤があって、その上に、水がたまっているという事でしょうか。
それにしても、下地島には、池が多く、
探検隊をはじめて、6っの未知の池に行きました。
陥没ドリーネの神秘!
内陸の池も海水ほどではないですが、塩辛いです。
それにしても、白鳥の潮吹き岩、生きてる間に復活の吹き上げを見たいです。
これは、ドリーネの竪穴と波による横穴がつながったものですね。
それをコンクリートで固めてしまうなんて。
池といえば、この日の最後、通り池に浮かぶゴミを視察したのですが、
20個程の発泡スチロールが浮かんでいます。
醜いです。
岩の上から、池面まで、最短で5メートル。
飛び込んで、ゴミを集めて、上からひっぱって、縄梯子で登ってくる案が出ました。
いかに、です。
妙案はありましょうか。
Posted by ちかさん at 2008年05月01日 04:06
伊良部島の水の話題が続きます。
> 「ひょうたん島!?」と家内と笑いました。
> 実際は,島尻マージの固い岩盤があって、その上に、水がたまっているという事でしょうか。
たしか、伊良部島の場合は宮古島と違って、島の最下部には島尻泥岩層という不透水基盤があって、その上の琉球石灰岩の層の部分に海水が浸透しています。そして、その上に雨水など淡水が溜まった構造になっていると思います。確かそのような状態を”淡水レンズ”と呼んでいたと思います。
(ネット検索で”淡水レンズ”のキーワードで調べれば詳しい説明が出るでしょう。) ちょうど、通り池の下部は海水で上部は淡水になっているのと良く似ています。違うのは海水が琉球石灰岩の層に染みこんでいる点でしょう。
そういう風な構造ですから、処理されない生活排水や畑の化学肥料などは雨水と一緒に”炭水レンズ”の部分つまり地下水に溜まります。それは水道水の元となる部分に流れ込んでいると考えた方が良いでしょう。しかし、現在は水道の水質については心配はないと思います。現在の伊良部島の水道水は確か「逆浸透膜法」とかいう処理方法で処理されていると思いますので、人の口に入る水質としては問題ないレベルになっていると思います。
でも、やはり人の暮らしが地下水を汚染する訳ですし、渡口の浜から長山へ続く道路沿いの高台に、長い間島のゴミを燃やし続けて来た場所も有ります。たぶん・・・調べればダイオキシンなどが発生しているかもしれませんので、これからは環境問題にも配慮した島の暮らし方が望まれると思います。
それから私が先のコメントで「伊良部島のことを「癒しの島」として紹介されていますが、たぶんそれは島のそんな地下構造と関係があるのではないか・・・と感じています。」と書いたのは、そんな島の地下構造からすると、地下に浸透した海水ために島全体の電位差が非常に少なくなっているのではないかと考えているからです。(確か塩水の方が真水より通電性が良かった?と記憶しています。)
電位差が少ないとなぜ良いのかは分かりませんが、一般にイヤシロチ、ケガレチとかいう土地の善し悪しを分ける一つの方法としてこの土地の電位差が少ない方が良いと言われているようなのです。 その意味ではたぶん伊良部島は日本でも有数の電位差の少ない土地ではないかと思います。まあ、そうは考えても、実際は現地で測定して調べてみないとホントの事はなんとも言えませんが・・。
ちかさんの、”白鳥の潮吹き岩、生きてる間に復活の吹き上げを見たいです。”のコメントにもあるように、ぜひ、アメリカのイエローストーン公園の間欠泉のように高く潮を噴き上げる様を見てみたいですね。
そういえば、どっかで海水のしぶきをかぶる土地のネギが潮のためか甘みを増して美味しいネギが育っていたという記事を見たことがあります。それを知った農家の方はわざわざ海水をくんで噴霧器で畑のネギにかけて甘いネギ作りをしていたような・・?!。
もしかしたら伊良部島でもその潮吹き岩の近くでは他と違う味の野菜が出来ていたかもしれませんね。ただ、一般的には海水をかぶると野菜などはやられてしまうので、嫌われたのでしょうが・・・。
> 池といえば、この日の最後、通り池に浮かぶゴミを視察したのですが、
> 20個程の発泡スチロールが浮かんでいます。
> 妙案はありましょうか。
ゴミ拾いのこんな案はどうでしょう。?
池の周囲の3,4箇所から相互にロープを張って、その交差する点に滑車をつけます。その滑車のポイントからロープを下に垂らして小さなネット状の物を取り付けて、上げ下げするような仕掛けを作ります。もちろんゴミがそのネットの中にうまく入るようにネットをコントロールするロープを付けて、対岸からロープを引いたり緩めたりしてやることが必要になるでしょうが。あとはゴミ有る場所の上部に滑車が移動するように、池の周囲でロープを持った人がそれぞれのロープを引いたり緩めたりするのです。
この方法なら4,5人の人手と池の直径+α程度の長いロープ数本と滑車、ゴミをすくうネットとその下部に付ける重り、ネットをうまく広げる工夫などがあれば出来るのではないか・・・・と考えますが。
まあ、そんなこんな不思議いっぱいの伊良部島。
これからも探検隊の活動が続くことを願っています。
Posted by 成田の住人 at 2008年05月10日 11:49
☆ 成田の住人さん
たくさんの示唆に富むコメントありがとうございます。
コメント中にあるイヤシロチ、ケガレチから検索して、
妻がかつて聞いたことがあるという、O(オー)リングという、
その地・その物体のエネルギーの良し悪しを測る方法に行き当たりました。
実際にやってみて、その的確さにびっくりしています。
二人1組で、ひとりが、調べるものに手をかざたり触れたりし、一方の手の親指と人差し指で丸を作ります。
もう一方の人が、手でそのリングを開く方向で力を加えます。
エネルギーがよいと動きません。
悪いと開いてしまいます。
作物や製品等でやっても的確です。
エネルギーセンサーになりそうです。
びっくりしています。
たくさんの示唆に富むコメントありがとうございます。
コメント中にあるイヤシロチ、ケガレチから検索して、
妻がかつて聞いたことがあるという、O(オー)リングという、
その地・その物体のエネルギーの良し悪しを測る方法に行き当たりました。
実際にやってみて、その的確さにびっくりしています。
二人1組で、ひとりが、調べるものに手をかざたり触れたりし、一方の手の親指と人差し指で丸を作ります。
もう一方の人が、手でそのリングを開く方向で力を加えます。
エネルギーがよいと動きません。
悪いと開いてしまいます。
作物や製品等でやっても的確です。
エネルギーセンサーになりそうです。
びっくりしています。
Posted by ちかさん at 2008年05月31日 05:30
上記の私のコメントについてちょっと訂正です。
私は勘違いして「電位差は少ない方が良い・・・」と書きましたが、実はそうではなくて、「地表部が地中部より電位が高く(プラス電位)、かつ電位差が大きい方が良い。」とのことのようです。 まあ、何事も曖昧な記憶で書いてはいけませんね。
でも、伊良部島の地下の構造が島尻泥岩層、地下に浸透した海水、その地下の海水の上に浮かぶように溜まった淡水レンズ層、そしてその上に琉球石灰岩と地表の土というサンドイッチ状になっているでしょうから、その構造が何らかの良い影響を島全体に及ぼしていると思います。(と言っても、これも推測ですが・・・。)それが島全体をイヤシロチ化しているのでは・・・と思っています。
そんなイヤシロチの話しを探っていくと「静電三法」という言葉にぶつかります。 私も良くは知りませんが、農業分野ではニワトリのえさにこの理論に基づいて電圧を与えて農薬の害を減少したり、食堂などでは水に電圧を加えて水の浄化?をするなどの装置があるようです。(たしか電子水とか言ってました。)宮古島でも市内の食堂がこの装置(高電圧の碍子の足が付いたステンレス製の水タンクを店内に設置して、お客に出す水を処理していたと記憶しています。)ただ、効果の程は知りませんが・・・。でも、何となくホントかな?- と思えるところが不思議です。
上記のOリングの話しも不思議ですよね。
私は勘違いして「電位差は少ない方が良い・・・」と書きましたが、実はそうではなくて、「地表部が地中部より電位が高く(プラス電位)、かつ電位差が大きい方が良い。」とのことのようです。 まあ、何事も曖昧な記憶で書いてはいけませんね。
でも、伊良部島の地下の構造が島尻泥岩層、地下に浸透した海水、その地下の海水の上に浮かぶように溜まった淡水レンズ層、そしてその上に琉球石灰岩と地表の土というサンドイッチ状になっているでしょうから、その構造が何らかの良い影響を島全体に及ぼしていると思います。(と言っても、これも推測ですが・・・。)それが島全体をイヤシロチ化しているのでは・・・と思っています。
そんなイヤシロチの話しを探っていくと「静電三法」という言葉にぶつかります。 私も良くは知りませんが、農業分野ではニワトリのえさにこの理論に基づいて電圧を与えて農薬の害を減少したり、食堂などでは水に電圧を加えて水の浄化?をするなどの装置があるようです。(たしか電子水とか言ってました。)宮古島でも市内の食堂がこの装置(高電圧の碍子の足が付いたステンレス製の水タンクを店内に設置して、お客に出す水を処理していたと記憶しています。)ただ、効果の程は知りませんが・・・。でも、何となくホントかな?- と思えるところが不思議です。
上記のOリングの話しも不思議ですよね。
Posted by 成田の住人 at 2008年05月31日 10:45